「アットホームという表記の何が問題なんだ?人間関係が良いに越したことははいだろう?」
という疑問に対してアットホームという表記が求職者からしたら「地雷求人」だと思われる5つの理由を解説します。
- 「それ以外の売りがない」と思われる
- アットホームかどうかは入社してからでないとわからない
- アットホームと謳っていても入社すると実際はそうじゃなかった
- 求職者にとってのアットホームと会社側が考えるアットホームのイメージが違う可能性
- すでにいる職員同士ではアットホーム かもしれないが新人からしたら入りづらい(すでにグループが出来上がってしまっていて)
おしながき
1.「それ以外の売りがない」と思われる

アットホーム以外の表現についてもそうだが、
ずっと日々いろんな求人を見ていて思ったことがある。
それは、「どこも同じようなことばかり言ってるな」と(一部そうじゃない求人もある)。
社会貢献、ありがとうを言われる、同じような給料、待遇などなど…
こんなんじゃいざ求職者が自力で転職活動したとき、結局どこに面接を受けに行けばいいかもわからない。
どこも同じようなことを言ってて、求職者からしたらその事業所の良さが見えてこないからだ。
そうなると「またか…」って反応になる。
綺麗事や他とも同じような文言に求人を見てる側は嫌気がさしてるということを知ってほしい。
2.アットホームかどうかは入社してからでないとわからない
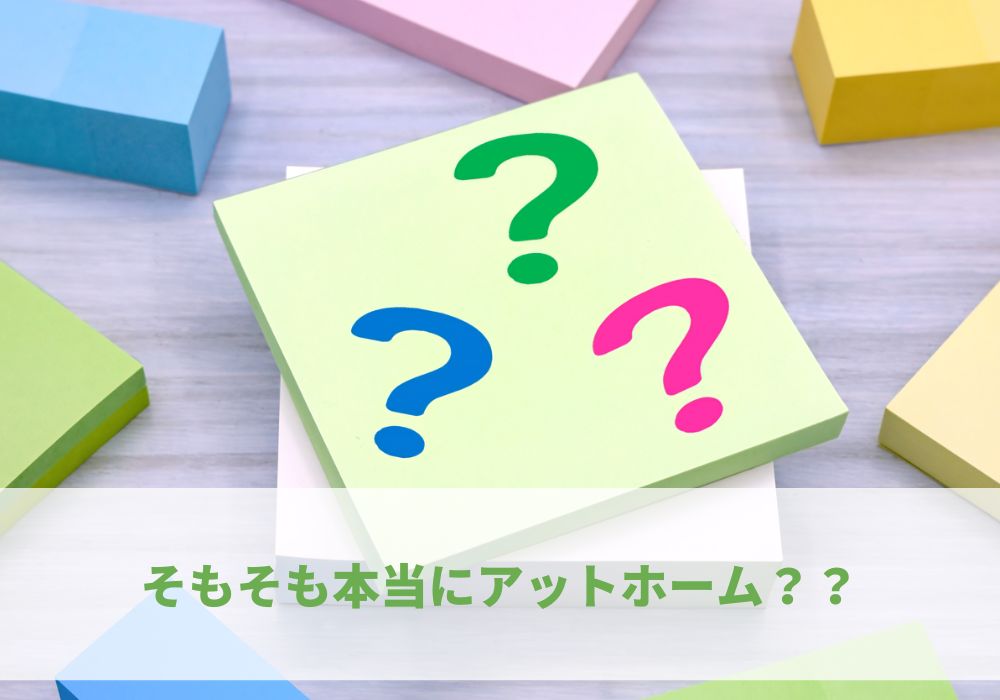
ここで言うアットホームは人間関係が良いとか、会社が従業員を大切にするといった定義だとする。
そうなると、それは結局入ってみないと実際はわからない。
そして入ってみないことわからないことを表立って一生懸命言われても、求職者からしたら
「信憑性なし」なのだ。
「絶対に儲かります!」
「これをすれば治ります!」
「私たちと関われば幸せになれます」
みたいな、あなただって、確認のしようがないのに、
本当かどうかわからないことを延々と言われ続けたら余計に不安になるでしょう?
3.アットホームと謳っていても入社すると実際はそうじゃなかった

入社してみると全然アットホームじゃない。
これは結構転職経験者は結構あるある…
入ってみると人間関係ギスギスしてたり、新人辞めさせるお局がいたり、経営者がくせ者だったり…
もう詐欺じゃんこれって…
こんなことだから「アットホーム」という表現が余計に警戒される。
4.求職者にとってのアットホームと会社側が考えるアットホームのイメージが違う可能性
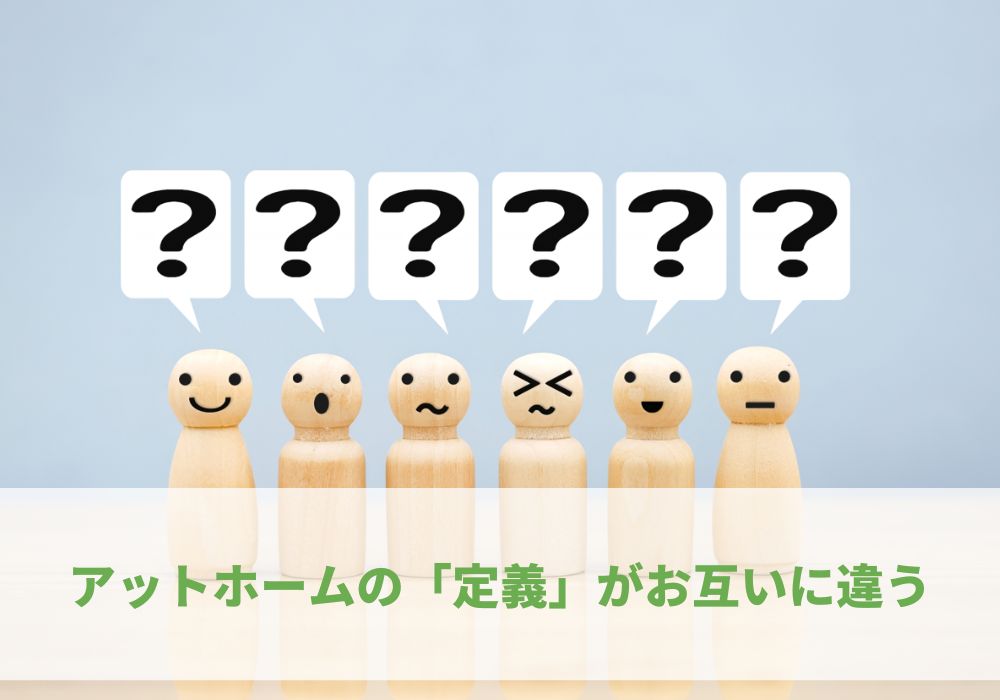
たとえば、求人を出す企業側が社員を家族のようにプライベートまで一緒にいるような関係性を作ろうと考えるのがアットホームだとしよう。
しかし、求人を見た求職者が思うアットホームの意味が「職員同士がみんな仲良しで常に助け合っている職場、人間関係のトラブルが全くない職場」だとイメージしてたらどうなるか?
実際に入ってみると、職員は仲良が良いわけでもなく、休日や仕事終わりにになると会社の飲み会や食事会に強制参加させられるみたいなこと起こったらどう思うだろうか?
ただ単にアットホームという言葉だけを使っても両者にとってアットホームの定義が違うと、
そこで両者の関係性に「摩擦」が起きる。
〇〇のひとつ覚えのように「アットホーム」という言葉だけを使うのではなく、
具体的にどうアットホームなのか言えないのならそもそもその言葉は求人には使わない方がいい。
5.すでにいる職員同士ではアットホーム かもしれないが新人からしたら入りづらい(すでにグループが出来上がってしまっていて)
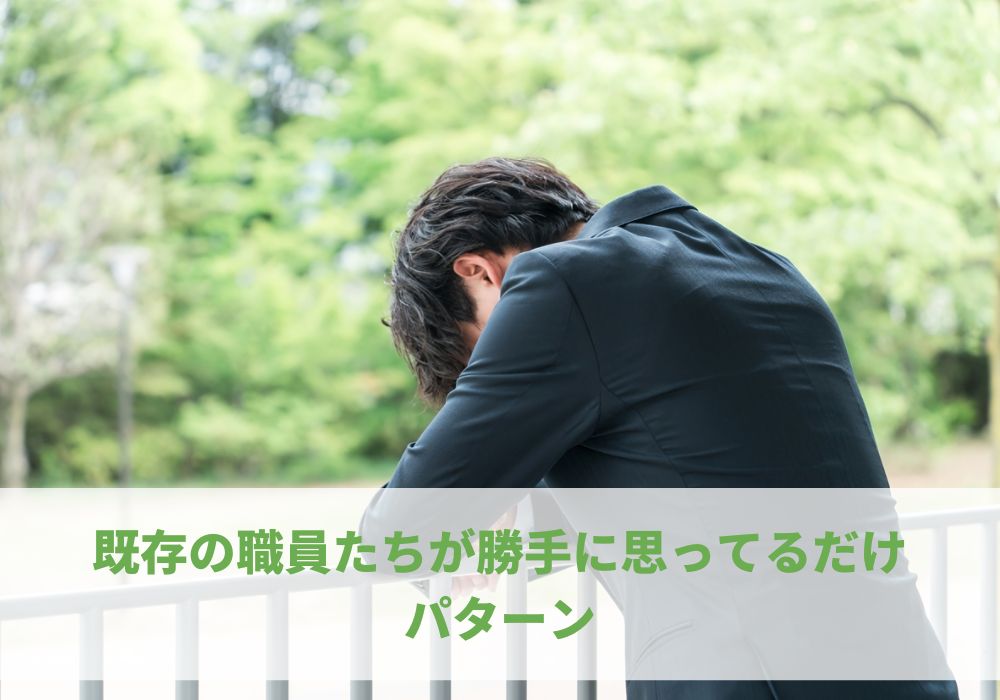
既存の職員にとっては仲良くてアットホームかもしれないが、入ってくる新人さんにとっては入りづらい雰囲気の場所もある。
本人の性格などいろんな要素もあるかもしれないが、結局職場に合わせて性格を変えるわけにもいかない以上、その人にとってはアットホームじゃないということも十分起こりえるのだ。
まとめ
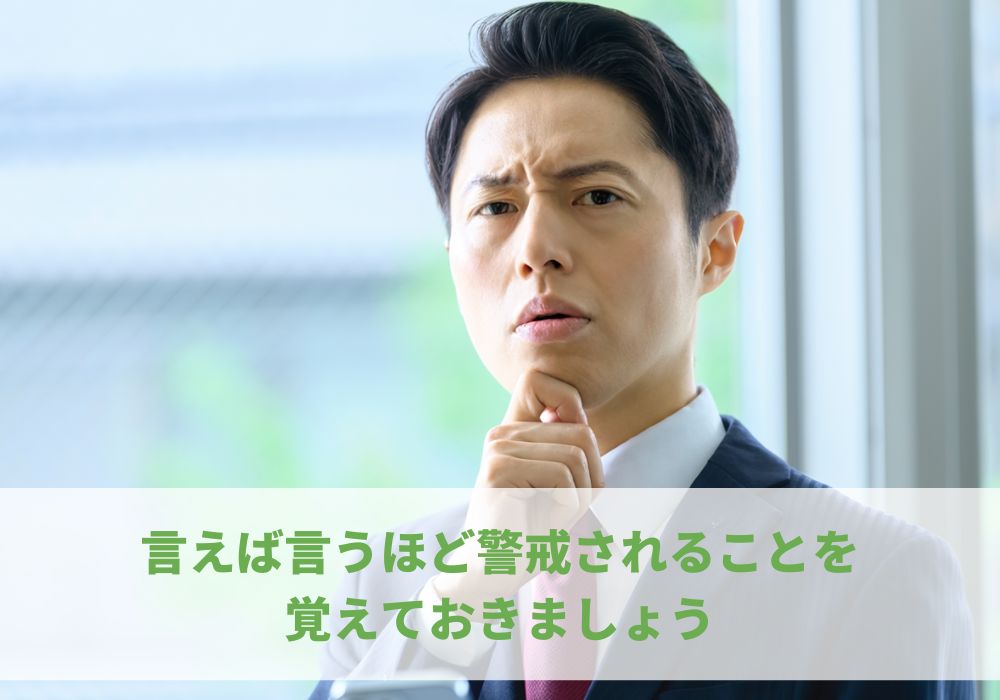
今回はアットホームという求人表現が求職者側からしたら地雷求人に思われる理由をお話ししました。
求人を出す側は、安易にアットホームアットホーム連呼するのではなく、
「求職者が転職先に何を求めているのか」
「安易な言葉を使うのではなく、具体的な事業所の売り」
これらをきちんと理解して求職者がイメージできるように訴えかけるのが得策ではなかろうか?
もちろん、嘘や誇大広告は絶対ダメ。
とにかく、転職に慣れてる人たちはそのセリフに嫌気がさしているということはわかってほしい。

